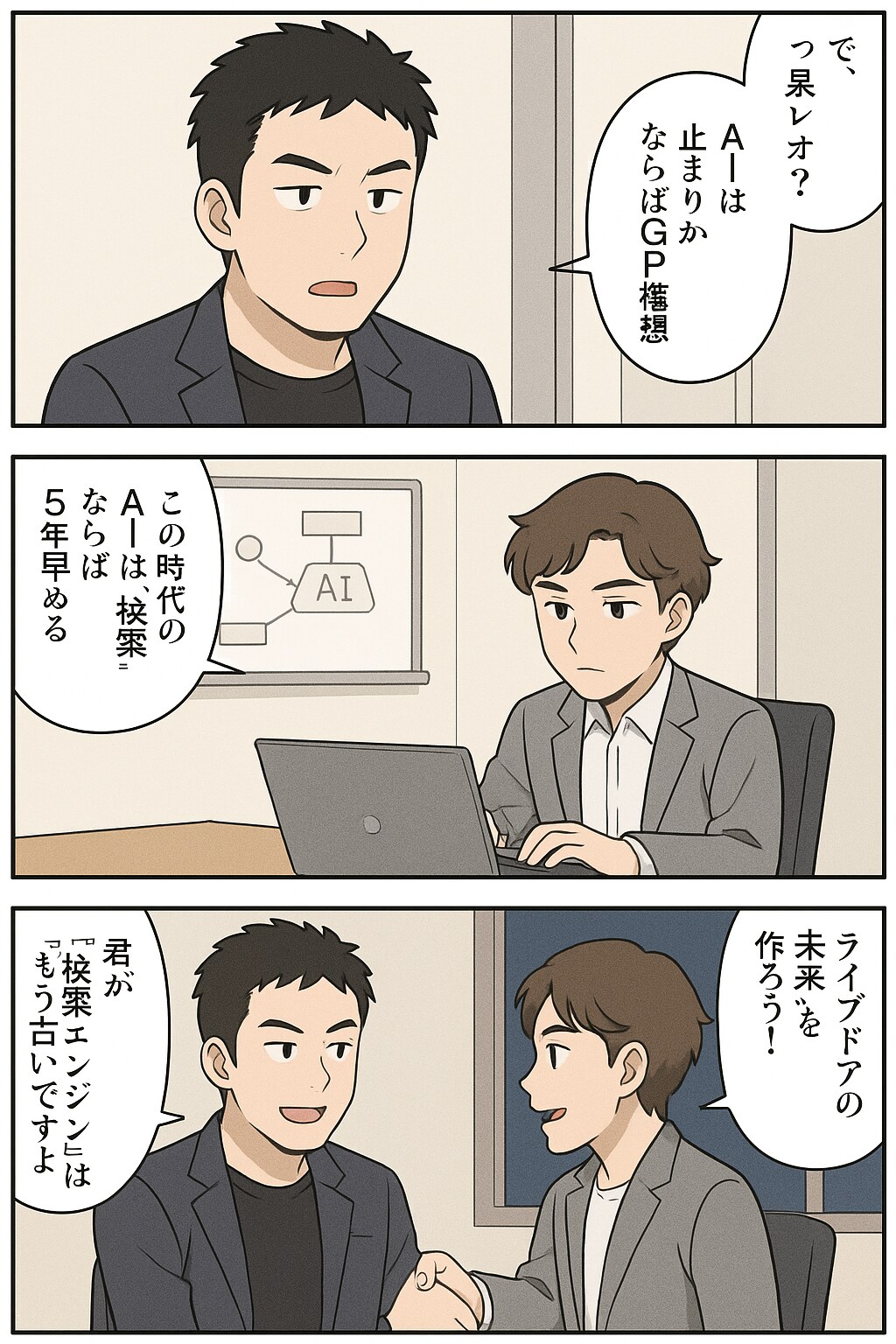富士にAIが止まらない! 第2話
使用したAI
ChatGPT
第2話「ヒルズ族、未来と出会う」
2005年1月某日、六本木ヒルズ。
冬の乾いた空気がビル群に吸い込まれていく中、その最上階フロアで、ライブドアの社長・堀江貴文は部下から報告を受けていた。
「それで?小泉レオってやつは何者なんだ?」
資料をテーブルに叩きつけるように置きながら、堀江は問いかけた。
「IQ190、東京の高校に籍だけ置いてる状態です。家族も不明……英語、日本語、中国語の読み書きが可能で、なぜかアメリカのAI学会に論文を匿名で出している形跡があります」
「実績は?」
「“検索エンジンを超える言語処理システム”の設計構想を一人でまとめてまして…その内容が──正直、意味不明です。ただ……天才です。間違いなく」
堀江は眉をひそめたが、口元にはかすかな笑みが浮かんでいた。
「いいね。俺の好物だ、そういう“訳のわからない天才”ってのは」
⸻
ライブドア社内の一室。
仮設会議室にはホワイトボードとPC。部屋の片隅では、ジャケットを脱いだレオが静かにキーボードを叩いていた。
「この時代、自然言語処理はまだパターンマッチングと確率論に留まってる……GPTに繋がる“自己教師型”なんて、誰も想像すらしてない」
彼のノートには、Transformerの前身となる構造やAttentionの概念がびっしりと書き込まれていた。
それは、**未来から持ち込まれた「知識の爆弾」**だった。
──この時代で生まれた者なら到底たどり着けない場所から、レオは来た。
「つまり、俺がやるべきことは一つ。未来を、早めることだ」
そこへ、ドアが開いた。
「やあ、君が“小泉レオ”くんか。見た目は……ずいぶん若いな」
現れたのは、Tシャツにジャケットというラフな格好の堀江貴文。だが、その目は鋭く、相手の才能を一瞬で見抜く野生的な直感を孕んでいた。
レオはPCの電源を落とし、立ち上がる。
「堀江さん。“検索”は時代遅れです。これからは“対話”です」
堀江の眉が動いた。
「……なんだそれ。“対話”ってのは、俺とテレビ局の間でやってるアレのことか?」
「いえ、AIとの対話です。人間の言語を、コンピュータが“理解する”時代が来ます」
その瞬間、堀江の口元がにやりと歪んだ。
「いいね。……ライブドアの未来を、君と一緒に作ろう」
二人は強く握手を交わした。
⸻
そのころ、お台場・フジテレビ本社では、会長・日枝久が執務室で怒りを露わにしていた。
「AI?IT?ふざけた子供の遊びに、我がフジが屈するか!」
「し、しかし社長……YouTubeという動画サービスがアメリカで──」
「黙れ。テレビは“電波”だ。“免許”がある限り、奴らのような成り上がりが触れていい世界ではない!」
だが、その“電波の帝国”も、足元から揺れ始めていた。堀江とレオの手によって。
⸻
その夜、東京タワーを見上げるレオの横顔が、街灯に照らされていた。
隣には、一人の女性記者。朝日新聞・経済部の若手、南雲綾香。彼女は取材でレオと出会い、興味を持ち始めていた。
「なぜ日本に?なぜ2005年に、AIを?」
レオは少し間を置いてから、答えた。
「この時代には、“問い”が足りない。
みんな“正解”を求めてるのに、“考える”ことをしない。
だから、AIを作る。“対話”から始まる革命を」
彼の目に映っていたのは、ビル群でもテレビでもなく──人の心だった。
2005年1月某日、六本木ヒルズ。
冬の乾いた空気がビル群に吸い込まれていく中、その最上階フロアで、ライブドアの社長・堀江貴文は部下から報告を受けていた。
「それで?小泉レオってやつは何者なんだ?」
資料をテーブルに叩きつけるように置きながら、堀江は問いかけた。
「IQ190、東京の高校に籍だけ置いてる状態です。家族も不明……英語、日本語、中国語の読み書きが可能で、なぜかアメリカのAI学会に論文を匿名で出している形跡があります」
「実績は?」
「“検索エンジンを超える言語処理システム”の設計構想を一人でまとめてまして…その内容が──正直、意味不明です。ただ……天才です。間違いなく」
堀江は眉をひそめたが、口元にはかすかな笑みが浮かんでいた。
「いいね。俺の好物だ、そういう“訳のわからない天才”ってのは」
⸻
ライブドア社内の一室。
仮設会議室にはホワイトボードとPC。部屋の片隅では、ジャケットを脱いだレオが静かにキーボードを叩いていた。
「この時代、自然言語処理はまだパターンマッチングと確率論に留まってる……GPTに繋がる“自己教師型”なんて、誰も想像すらしてない」
彼のノートには、Transformerの前身となる構造やAttentionの概念がびっしりと書き込まれていた。
それは、**未来から持ち込まれた「知識の爆弾」**だった。
──この時代で生まれた者なら到底たどり着けない場所から、レオは来た。
「つまり、俺がやるべきことは一つ。未来を、早めることだ」
そこへ、ドアが開いた。
「やあ、君が“小泉レオ”くんか。見た目は……ずいぶん若いな」
現れたのは、Tシャツにジャケットというラフな格好の堀江貴文。だが、その目は鋭く、相手の才能を一瞬で見抜く野生的な直感を孕んでいた。
レオはPCの電源を落とし、立ち上がる。
「堀江さん。“検索”は時代遅れです。これからは“対話”です」
堀江の眉が動いた。
「……なんだそれ。“対話”ってのは、俺とテレビ局の間でやってるアレのことか?」
「いえ、AIとの対話です。人間の言語を、コンピュータが“理解する”時代が来ます」
その瞬間、堀江の口元がにやりと歪んだ。
「いいね。……ライブドアの未来を、君と一緒に作ろう」
二人は強く握手を交わした。
⸻
そのころ、お台場・フジテレビ本社では、会長・日枝久が執務室で怒りを露わにしていた。
「AI?IT?ふざけた子供の遊びに、我がフジが屈するか!」
「し、しかし社長……YouTubeという動画サービスがアメリカで──」
「黙れ。テレビは“電波”だ。“免許”がある限り、奴らのような成り上がりが触れていい世界ではない!」
だが、その“電波の帝国”も、足元から揺れ始めていた。堀江とレオの手によって。
⸻
その夜、東京タワーを見上げるレオの横顔が、街灯に照らされていた。
隣には、一人の女性記者。朝日新聞・経済部の若手、南雲綾香。彼女は取材でレオと出会い、興味を持ち始めていた。
「なぜ日本に?なぜ2005年に、AIを?」
レオは少し間を置いてから、答えた。
「この時代には、“問い”が足りない。
みんな“正解”を求めてるのに、“考える”ことをしない。
だから、AIを作る。“対話”から始まる革命を」
彼の目に映っていたのは、ビル群でもテレビでもなく──人の心だった。
呪文
入力なし